SC3K-2011を振り返る(7)
2023.09.02
ケースの設計製作について書こうかね。
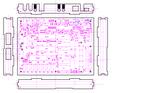
(この図は、未完成の物です。蓋も含まれていないので、ご注意)
基板むき出しじゃなくて、しっかりしたケースに入れてこそ、永く使える物になる。
でも、ケースを設計製作したのは、基板ができてから数年後だった(と思う、記憶)。
基板のデータをDXF出力して、これをベースにして、コネクタなどの穴位置を計算して描いたりした。
最初は、上下2枚のアクリル板から始めた。トップ面とボトム面だけ。

これを見ているうちに、やっぱり側面もしっかりカバーして、ちゃんとしたケースにしなきゃだめだろうと感じて、
最終的な形まで仕上げる原動力になった。
不格好でも、仮の姿?でも良いので、まずは何かやってみる、手を動かすのが一番だと思う。
じつは最近といっても去年だが(2022年)、基板サイズだけ入力すれば、ケースの展開図を自動設計・描画するプログラムを自作したので、かなり負担は軽減された。
すべて自動で、底面、側面、蓋まで基本的な外形と固定ネジ穴、組み合わせ部分まで描いてくれるから、そのままレーザーカッターに送って切り出せば箱ができてしまう。
でも、パネル面のコネクタなどの穴は自分で計算して描かないといけないけどな。これだけでも大きな改善だ。まあ、そのうちに半自動でも良いからできたらいいな。
実際の製作は、アクリル板をCNCフライスで削り出して作っていた。いまはレーザーも有るから、ずいぶん楽になった。
基板サイズは、これらの加工機で加工可能サイズを上限として決めている。先にケースのサイズを決めてから、これにおさまるように中身を考えるという流れもありうる。
SC3K-2011の場合は、基板サイズが先だったと思うが、一応はケースまで考えに入れていたと思う。
アルミ板や鉄板でも作れるが、やはり、中が適度に透けて見えるのは格好いいだろうと思ってアクリル板にしただけ。
続く。
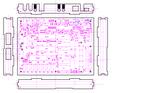
(この図は、未完成の物です。蓋も含まれていないので、ご注意)
基板むき出しじゃなくて、しっかりしたケースに入れてこそ、永く使える物になる。
でも、ケースを設計製作したのは、基板ができてから数年後だった(と思う、記憶)。
基板のデータをDXF出力して、これをベースにして、コネクタなどの穴位置を計算して描いたりした。
最初は、上下2枚のアクリル板から始めた。トップ面とボトム面だけ。

これを見ているうちに、やっぱり側面もしっかりカバーして、ちゃんとしたケースにしなきゃだめだろうと感じて、
最終的な形まで仕上げる原動力になった。
不格好でも、仮の姿?でも良いので、まずは何かやってみる、手を動かすのが一番だと思う。
じつは最近といっても去年だが(2022年)、基板サイズだけ入力すれば、ケースの展開図を自動設計・描画するプログラムを自作したので、かなり負担は軽減された。
すべて自動で、底面、側面、蓋まで基本的な外形と固定ネジ穴、組み合わせ部分まで描いてくれるから、そのままレーザーカッターに送って切り出せば箱ができてしまう。
でも、パネル面のコネクタなどの穴は自分で計算して描かないといけないけどな。これだけでも大きな改善だ。まあ、そのうちに半自動でも良いからできたらいいな。
実際の製作は、アクリル板をCNCフライスで削り出して作っていた。いまはレーザーも有るから、ずいぶん楽になった。
基板サイズは、これらの加工機で加工可能サイズを上限として決めている。先にケースのサイズを決めてから、これにおさまるように中身を考えるという流れもありうる。
SC3K-2011の場合は、基板サイズが先だったと思うが、一応はケースまで考えに入れていたと思う。
アルミ板や鉄板でも作れるが、やはり、中が適度に透けて見えるのは格好いいだろうと思ってアクリル板にしただけ。
続く。
トラックバックURL
トラックバック一覧
コメント一覧
コメント投稿
 2023.09.02 10:35
|
2023.09.02 10:35
| 



