最初の出会い
2023.12.28
私の最初のパソコンはSONY HB-101だった。
事前に色々迷ったが、買いに行ったところで、たまたま店に有って良さげだったのでそれに決めたっけ。
その前に、どれを買おうかとカタログを見たりしながら(予算も考えながら)迷っていた。
日立H1もいいなあ、でも高いな、カシオPV-7は安いな、でもメモリが少なくないか。あとで増やす?
MSXが良さそうだけど、MSX以外も検討してみるか、SC-3000もカシオのPV-7と同じような感じだな。BASIC内蔵な分だけ、PV-7のほうが良いか。
・・・こんなふうに迷っていた。
さて、SC-3000との出会いはHB-101購入後1年以上経過してからだった。
それは全くの偶然というか、何かのめぐり合わせ。
当時「ラジオの製作」という雑誌を定期購読していて、その売り買いコーナー。
「買い」ますコーナーなのに、SC-3000とソフト等をまとめて4.6Kで「売り」ます、って書いてある。
こりゃあ、間違って掲載したなと思い、(誰も気づいてない事を祈りながら)とりあえずその人に問い合わせてみたら、まだ売れてないという。
ラッキー、安価で一式揃ってしまった。
本体SC-3000H、BASIC L3B、ロードランナー、ジッピーレース、(名前忘れた)、ジョイスティック、電源アダプタ
その当時は、相手の住所・氏名・電話番号がそのまま掲載されており、基本的に本人と直接連絡をとりあって取引をしていた。文通欄も、読者の声のコーナーも同様だった。特に匿名希望にしない限り、そのまま掲載された。
掲載の文字数制限があったので、独特の略語があった。W〒は往復はがき。SASEは返信用封筒同封。Kは千円単位(例えば10Kなら1万円、0.7Kは700円)
個人情報の取り扱いにうるさい現代とは違って、おおらかな時代だった。
それだけに、いたずらや不幸の手紙を送るなどの問題もあった。
身内が漫画雑誌に文通友達の募集を載せたら、不幸の手紙がドッサリ届いて大ショック。
50通以上は有っただろうか、切手を貼ってないものが多く、その意味では実害があった。
何が楽しくてわざわざこんな物を送ってくるのか意味不明だった。
普通に文通の申し込みで来た手紙も、多くて処理しきれない。返事くれないんですか、無視ですかってキレちゃう人もいたと思う。もう、めちゃめちゃ。どうしようもない。処理が追いついてない。切手代もかかる。
子どもの頃だから、思いつきで文通の友達を募集したのかもしれないけど、これが現実の厳しさ。
でも、その中でも良い友達をみつけて長く続いたようで結果的には良かった。
脱線してしまったが、奇妙なめぐり合わせからSC-3000Hを手に入れてしまったというお話。
事前に色々迷ったが、買いに行ったところで、たまたま店に有って良さげだったのでそれに決めたっけ。
その前に、どれを買おうかとカタログを見たりしながら(予算も考えながら)迷っていた。
日立H1もいいなあ、でも高いな、カシオPV-7は安いな、でもメモリが少なくないか。あとで増やす?
MSXが良さそうだけど、MSX以外も検討してみるか、SC-3000もカシオのPV-7と同じような感じだな。BASIC内蔵な分だけ、PV-7のほうが良いか。
・・・こんなふうに迷っていた。
さて、SC-3000との出会いはHB-101購入後1年以上経過してからだった。
それは全くの偶然というか、何かのめぐり合わせ。
当時「ラジオの製作」という雑誌を定期購読していて、その売り買いコーナー。
「買い」ますコーナーなのに、SC-3000とソフト等をまとめて4.6Kで「売り」ます、って書いてある。
こりゃあ、間違って掲載したなと思い、(誰も気づいてない事を祈りながら)とりあえずその人に問い合わせてみたら、まだ売れてないという。
ラッキー、安価で一式揃ってしまった。
本体SC-3000H、BASIC L3B、ロードランナー、ジッピーレース、(名前忘れた)、ジョイスティック、電源アダプタ
その当時は、相手の住所・氏名・電話番号がそのまま掲載されており、基本的に本人と直接連絡をとりあって取引をしていた。文通欄も、読者の声のコーナーも同様だった。特に匿名希望にしない限り、そのまま掲載された。
掲載の文字数制限があったので、独特の略語があった。W〒は往復はがき。SASEは返信用封筒同封。Kは千円単位(例えば10Kなら1万円、0.7Kは700円)
個人情報の取り扱いにうるさい現代とは違って、おおらかな時代だった。
それだけに、いたずらや不幸の手紙を送るなどの問題もあった。
身内が漫画雑誌に文通友達の募集を載せたら、不幸の手紙がドッサリ届いて大ショック。
50通以上は有っただろうか、切手を貼ってないものが多く、その意味では実害があった。
何が楽しくてわざわざこんな物を送ってくるのか意味不明だった。
普通に文通の申し込みで来た手紙も、多くて処理しきれない。返事くれないんですか、無視ですかってキレちゃう人もいたと思う。もう、めちゃめちゃ。どうしようもない。処理が追いついてない。切手代もかかる。
子どもの頃だから、思いつきで文通の友達を募集したのかもしれないけど、これが現実の厳しさ。
でも、その中でも良い友達をみつけて長く続いたようで結果的には良かった。
脱線してしまったが、奇妙なめぐり合わせからSC-3000Hを手に入れてしまったというお話。
SC3K-2011を振り返る(8)
2023.09.03
次は、SC3K-2011本体の話はチョット脳の奥から出てこないから、脇道にそれて、関連した話でも書いていれば何か思い出すだろう。
カートリッジ基板 MPC-S3KL3 について。

忘れたが、ROMとSRAMを外付けしようと思ったんだっけ。
RAMが有るのでBASICが動かせる。
自作プログラムを動かすのにも役立つかもしれない。
実際のカートリッジケースと基板を採寸して、基板を設計するところから始めた。
ケースも作りたいが、まずは基板を作ればテストが進められる。
MSXのように、規格として寸法図などが書籍に載っていないから、自分で調べるしかない。
まあ、MSXの時も大変だったけれど。
テクハンも持っていなかったから(昔、そんな高い本は買えなかったから友達のを借りて、最低限必要なところだけ書き写したりしていた)、国立国会図書館から複写を取り寄せた。
古本を探してもなかなか無かったし・・・。
その国会図書館の複写、知りたい所(カートリッジの寸法など)のページがわからないから、まずは目次の複写を取り寄せ、それを見てページを推定し、改めて何ページから何ページまでの複写を申し込む。ここまでで何週間もかかった。
脱線するけど、最初にMSXユニバーサル基板を設計・製作した時は、サンハヤトのMCC-159が1枚だけ手元にあって、それを採寸するところから始めた。
何度も使いまわしてボロボロになったやつだ。
学生の頃は金がないから、1枚の基板を使いまわして、いろんな作品を作った。だから作品が残ってないわけだ。
MPC-S3KL3の話に戻る。
いまさらDRAMでもないし、SRAMを搭載すればバッテリーバックアップ可能になる。昔、夢見たバッテリーバックアップが実現できる。
妄想としては、電源ONでBASIC起動したら、途中まで打ち込んでいたプログラムがそのまま残っていて続きができる、といった具合だ。
実際にやってみたら、RAMは毎回初期化されるのでそううまくはいかなかったが、パッチ等で解決したと思う。(だいぶ前の話)
当時あまり意識しなかったがポケコンは便利だった。いつでも使いたい時に電源ONしてプログラムを打ち込み、ほっといても自動的にOFFになり、またONにすればプログラムは残っていて続きができたもんなあ。
続く。
カートリッジ基板 MPC-S3KL3 について。

忘れたが、ROMとSRAMを外付けしようと思ったんだっけ。
RAMが有るのでBASICが動かせる。
自作プログラムを動かすのにも役立つかもしれない。
実際のカートリッジケースと基板を採寸して、基板を設計するところから始めた。
ケースも作りたいが、まずは基板を作ればテストが進められる。
MSXのように、規格として寸法図などが書籍に載っていないから、自分で調べるしかない。
まあ、MSXの時も大変だったけれど。
テクハンも持っていなかったから(昔、そんな高い本は買えなかったから友達のを借りて、最低限必要なところだけ書き写したりしていた)、国立国会図書館から複写を取り寄せた。
古本を探してもなかなか無かったし・・・。
その国会図書館の複写、知りたい所(カートリッジの寸法など)のページがわからないから、まずは目次の複写を取り寄せ、それを見てページを推定し、改めて何ページから何ページまでの複写を申し込む。ここまでで何週間もかかった。
脱線するけど、最初にMSXユニバーサル基板を設計・製作した時は、サンハヤトのMCC-159が1枚だけ手元にあって、それを採寸するところから始めた。
何度も使いまわしてボロボロになったやつだ。
学生の頃は金がないから、1枚の基板を使いまわして、いろんな作品を作った。だから作品が残ってないわけだ。
MPC-S3KL3の話に戻る。
いまさらDRAMでもないし、SRAMを搭載すればバッテリーバックアップ可能になる。昔、夢見たバッテリーバックアップが実現できる。
妄想としては、電源ONでBASIC起動したら、途中まで打ち込んでいたプログラムがそのまま残っていて続きができる、といった具合だ。
実際にやってみたら、RAMは毎回初期化されるのでそううまくはいかなかったが、パッチ等で解決したと思う。(だいぶ前の話)
当時あまり意識しなかったがポケコンは便利だった。いつでも使いたい時に電源ONしてプログラムを打ち込み、ほっといても自動的にOFFになり、またONにすればプログラムは残っていて続きができたもんなあ。
続く。
SC3K-2011を振り返る(7)
2023.09.02
ケースの設計製作について書こうかね。
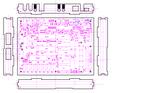
(この図は、未完成の物です。蓋も含まれていないので、ご注意)
基板むき出しじゃなくて、しっかりしたケースに入れてこそ、永く使える物になる。
でも、ケースを設計製作したのは、基板ができてから数年後だった(と思う、記憶)。
基板のデータをDXF出力して、これをベースにして、コネクタなどの穴位置を計算して描いたりした。
最初は、上下2枚のアクリル板から始めた。トップ面とボトム面だけ。

これを見ているうちに、やっぱり側面もしっかりカバーして、ちゃんとしたケースにしなきゃだめだろうと感じて、
最終的な形まで仕上げる原動力になった。
不格好でも、仮の姿?でも良いので、まずは何かやってみる、手を動かすのが一番だと思う。
じつは最近といっても去年だが(2022年)、基板サイズだけ入力すれば、ケースの展開図を自動設計・描画するプログラムを自作したので、かなり負担は軽減された。
すべて自動で、底面、側面、蓋まで基本的な外形と固定ネジ穴、組み合わせ部分まで描いてくれるから、そのままレーザーカッターに送って切り出せば箱ができてしまう。
でも、パネル面のコネクタなどの穴は自分で計算して描かないといけないけどな。これだけでも大きな改善だ。まあ、そのうちに半自動でも良いからできたらいいな。
実際の製作は、アクリル板をCNCフライスで削り出して作っていた。いまはレーザーも有るから、ずいぶん楽になった。
基板サイズは、これらの加工機で加工可能サイズを上限として決めている。先にケースのサイズを決めてから、これにおさまるように中身を考えるという流れもありうる。
SC3K-2011の場合は、基板サイズが先だったと思うが、一応はケースまで考えに入れていたと思う。
アルミ板や鉄板でも作れるが、やはり、中が適度に透けて見えるのは格好いいだろうと思ってアクリル板にしただけ。
続く。
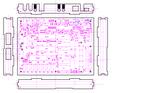
(この図は、未完成の物です。蓋も含まれていないので、ご注意)
基板むき出しじゃなくて、しっかりしたケースに入れてこそ、永く使える物になる。
でも、ケースを設計製作したのは、基板ができてから数年後だった(と思う、記憶)。
基板のデータをDXF出力して、これをベースにして、コネクタなどの穴位置を計算して描いたりした。
最初は、上下2枚のアクリル板から始めた。トップ面とボトム面だけ。

これを見ているうちに、やっぱり側面もしっかりカバーして、ちゃんとしたケースにしなきゃだめだろうと感じて、
最終的な形まで仕上げる原動力になった。
不格好でも、仮の姿?でも良いので、まずは何かやってみる、手を動かすのが一番だと思う。
じつは最近といっても去年だが(2022年)、基板サイズだけ入力すれば、ケースの展開図を自動設計・描画するプログラムを自作したので、かなり負担は軽減された。
すべて自動で、底面、側面、蓋まで基本的な外形と固定ネジ穴、組み合わせ部分まで描いてくれるから、そのままレーザーカッターに送って切り出せば箱ができてしまう。
でも、パネル面のコネクタなどの穴は自分で計算して描かないといけないけどな。これだけでも大きな改善だ。まあ、そのうちに半自動でも良いからできたらいいな。
実際の製作は、アクリル板をCNCフライスで削り出して作っていた。いまはレーザーも有るから、ずいぶん楽になった。
基板サイズは、これらの加工機で加工可能サイズを上限として決めている。先にケースのサイズを決めてから、これにおさまるように中身を考えるという流れもありうる。
SC3K-2011の場合は、基板サイズが先だったと思うが、一応はケースまで考えに入れていたと思う。
アルミ板や鉄板でも作れるが、やはり、中が適度に透けて見えるのは格好いいだろうと思ってアクリル板にしただけ。
続く。
SC3K-2011を振り返る(6)
2023.09.01
とりあえず(1)~(5)まで、自分の記憶を頼りに書いてみたが、久しぶりに(本当に久しぶり)自分のホームページの記事「復活!SC-3000(もどき)」を読むと、かなり重複があった。すでに書いていた内容だった。
何か新しい話でも書かないと面白くないなあ、と思ったのであった。
SC3K-2011の回路について・・・
・POWER LED
通電中は光るようにしたのだけど、現代風に青色とした。
ところが、実際に光らせてみるとまぶしい。基本的に高輝度だからな。昔の薄暗いLEDを知っている世代は、つい、抵抗値を低めに設定してしまう。暗かったんだよ。昔のLEDは。
5Vで4.7kΩにしても十分光ってるから、とんでもないよな。それで別の基板の部品実装を工場に頼んだ時、質問が来た。LEDの抵抗値が10kって間違いじゃないですか?って。
いえ、それは間違いじゃないんですよ。1kだとギラギラ明るすぎるからと説明。
わかっているのだけど、今でも「LEDには10mA以上流すようにしなければ」という意識がどこかに残っている。
・リセット回路
ここは真面目に作ったね。ちゃんと電圧検出のICまで組み込んである。
電子工作の本など見ると、たいていは手抜き(それが普通だと思われている)リセット回路で、抵抗、コンデンサ、ダイオードぐらいだろう。
現場で色々失敗した経験から、それ以来、電圧検出のICを組み込むようにした。
シュミットトリガの波形整形も入れてある。Z80のリセット端子に波形整形をしないままの立ち上がりの遅い波形なんか入れるとおかしくなる事があるぞ。
もう、最初からシュミットトリガで受けるように内蔵してくれないかなと昔思っていた。いまのPICマイコンなどは改善されてる。
さらに、外部リセットボタンが付けられるようにピンヘッダを出しておいた。これはROMエミュレータを使う時にも役立つだろう。
・VRAM
オリジナルのSC3KはMB8118等を使っていたけど、2011年当時すでに廃品種だから、パーツ屋では在庫限りだった。そこで、互換性を調べながら、使える部品の候補を広げてみた。
41256もそのまま差し替えできる。
MB8118のほかに、手持ちが有ったKM41256AP-15、TMM41256P-12、μPD41256C-15、M5M4256S-15をそれぞれテストしてOKだった。
それにしても日本メーカーの半導体が元気だった頃を思い出すね。KM41256はSAMSUNGだけど、他は富士通、東芝、NEC、三菱で。
1995年頃だったか、会社で「トラ技」を読んでいたら「三星半導体」(SAMSUNG)のDRAMの広告を見かけた。へえ、珍しいなあ。ちょうど先輩が覗き込んできて、「お前、そんな韓国製の部品なんか設計で使うもんじゃねえぞ」と。
ところが、いま振り返ってみると、もうその頃には日本の半導体は追い抜かれていたのだ。
・SN76489AN
DCSGと呼ぶのは、わりと最近まで知らなかった。型番しか馴染みがなかった。
・アドレスデコード等のロジック
結構ミスったな。
オリジナルのSC3Kの回路は、おそらくコストダウンが目的だろうけど、抵抗を組み込んでICを削減したりしている。
その部分の理解が足りなかったりしたので間違った。
抵抗を組み込んで? ってそれだけ書いても意味がわからないと思うが、長々と説明するのは大変だから回路図を見て。
初めて試作を組み上げた時、ロードランナーの画面が出た、で喜んだけど途中で止まったよな。音も出なかった。SN76489周辺の回路を修正して、ようやく動くように、音も出るようになった。
・8251とUSBシリアル、ボーレートジェネレータ
キンセキのEXO-3は便利だったのに、なんでやめるんだよと、廃止されたのはずいぶん昔のことだけど、今さらながら思う。
まあ、プログラマブルなオシレータは有るけどな。
・スロット
MSX用の信号が出せるように50PのBOXヘッダを設けたが、完全にはできなかった。必要な信号を作るためのICを載せるスペースも足りなかった。
続く。
何か新しい話でも書かないと面白くないなあ、と思ったのであった。
SC3K-2011の回路について・・・
・POWER LED
通電中は光るようにしたのだけど、現代風に青色とした。
ところが、実際に光らせてみるとまぶしい。基本的に高輝度だからな。昔の薄暗いLEDを知っている世代は、つい、抵抗値を低めに設定してしまう。暗かったんだよ。昔のLEDは。
5Vで4.7kΩにしても十分光ってるから、とんでもないよな。それで別の基板の部品実装を工場に頼んだ時、質問が来た。LEDの抵抗値が10kって間違いじゃないですか?って。
いえ、それは間違いじゃないんですよ。1kだとギラギラ明るすぎるからと説明。
わかっているのだけど、今でも「LEDには10mA以上流すようにしなければ」という意識がどこかに残っている。
・リセット回路
ここは真面目に作ったね。ちゃんと電圧検出のICまで組み込んである。
電子工作の本など見ると、たいていは手抜き(それが普通だと思われている)リセット回路で、抵抗、コンデンサ、ダイオードぐらいだろう。
現場で色々失敗した経験から、それ以来、電圧検出のICを組み込むようにした。
シュミットトリガの波形整形も入れてある。Z80のリセット端子に波形整形をしないままの立ち上がりの遅い波形なんか入れるとおかしくなる事があるぞ。
もう、最初からシュミットトリガで受けるように内蔵してくれないかなと昔思っていた。いまのPICマイコンなどは改善されてる。
さらに、外部リセットボタンが付けられるようにピンヘッダを出しておいた。これはROMエミュレータを使う時にも役立つだろう。
・VRAM
オリジナルのSC3KはMB8118等を使っていたけど、2011年当時すでに廃品種だから、パーツ屋では在庫限りだった。そこで、互換性を調べながら、使える部品の候補を広げてみた。
41256もそのまま差し替えできる。
MB8118のほかに、手持ちが有ったKM41256AP-15、TMM41256P-12、μPD41256C-15、M5M4256S-15をそれぞれテストしてOKだった。
それにしても日本メーカーの半導体が元気だった頃を思い出すね。KM41256はSAMSUNGだけど、他は富士通、東芝、NEC、三菱で。
1995年頃だったか、会社で「トラ技」を読んでいたら「三星半導体」(SAMSUNG)のDRAMの広告を見かけた。へえ、珍しいなあ。ちょうど先輩が覗き込んできて、「お前、そんな韓国製の部品なんか設計で使うもんじゃねえぞ」と。
ところが、いま振り返ってみると、もうその頃には日本の半導体は追い抜かれていたのだ。
・SN76489AN
DCSGと呼ぶのは、わりと最近まで知らなかった。型番しか馴染みがなかった。
・アドレスデコード等のロジック
結構ミスったな。
オリジナルのSC3Kの回路は、おそらくコストダウンが目的だろうけど、抵抗を組み込んでICを削減したりしている。
その部分の理解が足りなかったりしたので間違った。
抵抗を組み込んで? ってそれだけ書いても意味がわからないと思うが、長々と説明するのは大変だから回路図を見て。
初めて試作を組み上げた時、ロードランナーの画面が出た、で喜んだけど途中で止まったよな。音も出なかった。SN76489周辺の回路を修正して、ようやく動くように、音も出るようになった。
・8251とUSBシリアル、ボーレートジェネレータ
キンセキのEXO-3は便利だったのに、なんでやめるんだよと、廃止されたのはずいぶん昔のことだけど、今さらながら思う。
まあ、プログラマブルなオシレータは有るけどな。
・スロット
MSX用の信号が出せるように50PのBOXヘッダを設けたが、完全にはできなかった。必要な信号を作るためのICを載せるスペースも足りなかった。
続く。
SC3K-2011を振り返る(5)
2023.08.31
SC3K-2011を振り返る、とか書きながら、SC3K実機の話になってしまっているが、
まずはSC3K実機を思い出しながら、記憶をたどっていきたい。
カセットの接触不良で泣かされたのは良く有った話で(だけど当時は周囲にSC3K仲間がいなかったから知らなかった)、
自分なりに工夫してみたのは、紙を折ってスキマに挟んだりとか。
これは完璧な対策にはならなかったような気がするけど。
最終的には、意地になってカートリッジ端子とSC3K内部の基板を直結してしまった。
リード線を何十本も切って両端皮むきするのは大変な手間だったが、直結なら完全無欠だろう。
どうよ、バッチリだぜ、バンバン叩いても何とも無い。
これでしばらくの間はBASIC専用機として使っていたが、またゲームで遊びたくなり、仕方なく元に戻した。
なんという無駄なことでしょう。
SC3K実機の小ささと軽さは、あちこち持ち運ぶのにはちょうど良かった。学生カバンに入れて、中学校に持って行って教室のテレビにつないで遊んだ事がある。
HB-101(MSX)も同じようにしてカバンに入れてみたが、蓋をするのが厳しかった。しかも、どこかでひっかけてしまいCAPSキーを折ってしまった。仕方なく、中央に穴を開けてナベネジをつっこんで固定した。
当時持っていたSC3K実機は、確か高1か2の時に部品取りしてしまった。いま思えば、なんともったいない。でも当時は飽きてしまって、もういらないと思ったから仕方ない。
でも結果的には良かったのだ。これがSC3K-2011につながったのだから。
部品取りは小学生の頃からTVの部品を取り外していたから、熟練していた。Z80なんかも、マイナスドライバーを差し込んで浮かし気味にしながら、ハンダを滑らすように融かして、だんだん浮かせていた。片列浮けば楽勝だ。
ハンダ吸い取り線なんか持っていなかった。有るのははんだごてと糸ハンダだけ。吸い取り機なんか、ずいぶん後になってから買ったものだ。(手動ポンプ式のやつ)
分解しながら、回路図を起こそうと思ったが、パターンが細かくて追えなかった。いまなら(仕事で)慣れてるから余裕でできるけど、当時は、こんなの絶対無理だとあきらめてしまった。
それで結局、部品取りしてどうしたかというと、高校2年の春休みにワンボードマイコンを作った。
すでに当時(1988年頃)ワンボードマイコンを作ろうというヤツはいなかった。その10年以上前にブームは過ぎていただろう。
だが、勉強のために、あえて作ろうとした。
もとにした記事は「ラジオの製作」に載っていたZ80マイコンシステムで、本来はカードスロットに各ブロック毎(CPUボード、メモリボード、I/Oボードなど)を差し込んで構築するものだった。
その回路を自分なりに整理して、ワンボードに仕立てたというわけ。
当時の自分の実力としては、相当な冒険だった。
最初に一部だけ、CPUボードだけ作ってみたけれど、当然それだけでは動いているのかいないのか、動いていても正常なのか、テスター以外にはオシロも何もなく、ラジオでノイズを聞いてみて、うーん、なんか動いてる? その程度だった。
そうやっていじっているうちに、変な臭いがしてきて、74LS245が過熱していた。こりゃやばい。急いで電源を切った。壊しただろうなあ。
そこでメゲないで、改めて最初から丁寧に作ろうと決心して、3日間かけて作り上げたのだった。
とにかく1本1本、丁寧に進めることにした。回路図を赤鉛筆で塗りながら、間違いがないようにした。
こうして無事に動作するようになったのだが、このワンボードマイコンに使ったのがSC3Kから取り外したZ80だった。
そんなの取り外さなくても買ってくればいいでしょー、って言われそうなので説明する。
地方なのでパーツ屋はなかった。ホームセンターに電線とかハンダが置いてある程度。
どうしてもICなどは通販に頼るしかなかった。だが、お金はそんなに持ってないし、ごく限られたお金しか使えなかった。
部品表を作り、持っている部品をできるだけ活用するようにして、部品代を削りながら計算していった。どうしても買わないと揃わないものだけに絞り込み、通販で取り寄せた。
抵抗なんかも新品ではなく、テレビの基板からはずして集めたものを使っていた。そんなものは買っても安いのに、と思うのだけど、やはり簡単には買えないから、仕方なかった。
テレビの基板を持ってきて、お目当ての抵抗を、目を皿のようにして探すのである。このおかげで、カラーコードが瞬間的に読めるようになった。
確かに無駄なことに時間を費やしていたかもしれないが・・・。
最初の頃は基板からとにかく取り外して集めていたが、整理・分類ということを知らなかった為、ごっちゃまぜの山の中から探すことに時間を費やしていたっけ。
ばかなりに学習して、基板に付いた状態のほうが探しやすいなと気づいたわけ。(ずいぶん後になって)
続く。
まずはSC3K実機を思い出しながら、記憶をたどっていきたい。
カセットの接触不良で泣かされたのは良く有った話で(だけど当時は周囲にSC3K仲間がいなかったから知らなかった)、
自分なりに工夫してみたのは、紙を折ってスキマに挟んだりとか。
これは完璧な対策にはならなかったような気がするけど。
最終的には、意地になってカートリッジ端子とSC3K内部の基板を直結してしまった。
リード線を何十本も切って両端皮むきするのは大変な手間だったが、直結なら完全無欠だろう。
どうよ、バッチリだぜ、バンバン叩いても何とも無い。
これでしばらくの間はBASIC専用機として使っていたが、またゲームで遊びたくなり、仕方なく元に戻した。
なんという無駄なことでしょう。
SC3K実機の小ささと軽さは、あちこち持ち運ぶのにはちょうど良かった。学生カバンに入れて、中学校に持って行って教室のテレビにつないで遊んだ事がある。
HB-101(MSX)も同じようにしてカバンに入れてみたが、蓋をするのが厳しかった。しかも、どこかでひっかけてしまいCAPSキーを折ってしまった。仕方なく、中央に穴を開けてナベネジをつっこんで固定した。
当時持っていたSC3K実機は、確か高1か2の時に部品取りしてしまった。いま思えば、なんともったいない。でも当時は飽きてしまって、もういらないと思ったから仕方ない。
でも結果的には良かったのだ。これがSC3K-2011につながったのだから。
部品取りは小学生の頃からTVの部品を取り外していたから、熟練していた。Z80なんかも、マイナスドライバーを差し込んで浮かし気味にしながら、ハンダを滑らすように融かして、だんだん浮かせていた。片列浮けば楽勝だ。
ハンダ吸い取り線なんか持っていなかった。有るのははんだごてと糸ハンダだけ。吸い取り機なんか、ずいぶん後になってから買ったものだ。(手動ポンプ式のやつ)
分解しながら、回路図を起こそうと思ったが、パターンが細かくて追えなかった。いまなら(仕事で)慣れてるから余裕でできるけど、当時は、こんなの絶対無理だとあきらめてしまった。
それで結局、部品取りしてどうしたかというと、高校2年の春休みにワンボードマイコンを作った。
すでに当時(1988年頃)ワンボードマイコンを作ろうというヤツはいなかった。その10年以上前にブームは過ぎていただろう。
だが、勉強のために、あえて作ろうとした。
もとにした記事は「ラジオの製作」に載っていたZ80マイコンシステムで、本来はカードスロットに各ブロック毎(CPUボード、メモリボード、I/Oボードなど)を差し込んで構築するものだった。
その回路を自分なりに整理して、ワンボードに仕立てたというわけ。
当時の自分の実力としては、相当な冒険だった。
最初に一部だけ、CPUボードだけ作ってみたけれど、当然それだけでは動いているのかいないのか、動いていても正常なのか、テスター以外にはオシロも何もなく、ラジオでノイズを聞いてみて、うーん、なんか動いてる? その程度だった。
そうやっていじっているうちに、変な臭いがしてきて、74LS245が過熱していた。こりゃやばい。急いで電源を切った。壊しただろうなあ。
そこでメゲないで、改めて最初から丁寧に作ろうと決心して、3日間かけて作り上げたのだった。
とにかく1本1本、丁寧に進めることにした。回路図を赤鉛筆で塗りながら、間違いがないようにした。
こうして無事に動作するようになったのだが、このワンボードマイコンに使ったのがSC3Kから取り外したZ80だった。
そんなの取り外さなくても買ってくればいいでしょー、って言われそうなので説明する。
地方なのでパーツ屋はなかった。ホームセンターに電線とかハンダが置いてある程度。
どうしてもICなどは通販に頼るしかなかった。だが、お金はそんなに持ってないし、ごく限られたお金しか使えなかった。
部品表を作り、持っている部品をできるだけ活用するようにして、部品代を削りながら計算していった。どうしても買わないと揃わないものだけに絞り込み、通販で取り寄せた。
抵抗なんかも新品ではなく、テレビの基板からはずして集めたものを使っていた。そんなものは買っても安いのに、と思うのだけど、やはり簡単には買えないから、仕方なかった。
テレビの基板を持ってきて、お目当ての抵抗を、目を皿のようにして探すのである。このおかげで、カラーコードが瞬間的に読めるようになった。
確かに無駄なことに時間を費やしていたかもしれないが・・・。
最初の頃は基板からとにかく取り外して集めていたが、整理・分類ということを知らなかった為、ごっちゃまぜの山の中から探すことに時間を費やしていたっけ。
ばかなりに学習して、基板に付いた状態のほうが探しやすいなと気づいたわけ。(ずいぶん後になって)
続く。
 2023.12.28 12:47
|
2023.12.28 12:47
| 



