UFOの飛行原理
2025.08.13
「子供の科学完全読本 高度経済成長期編」より
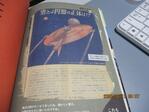
このイラストでは何か噴射してるけど、それは違うだろうと。
証言に基づいた想像図なので、必ずしも実物を示したものではないが、噴射するあたりは既成概念にとらわれているようだ。
やっぱり反重力か何かで、何も噴射せず、フワリと浮いてビュンと飛んでいかなきゃ空飛ぶ円盤じゃない。
どんな原理で飛んでいるのか、それは地球の人類にはまだわかってない。(エリア51あたりでは既に常識だろうけどな)
でも私は思います。それは案外、簡単なことかもしれません。
あー、なーんだ、そんなことだったのか。
わかってしまえば簡単だけれど、今はわかる前の段階、わからないからわからないという、何がわからないのかわからない、そんな感じ。
案外そんなものです。
新しいことに取り組む時、本を読んでも全然わからないし、試してみてもサッパリだし、なかなか思ったような結果がでないし、それでも執着して手を変え品を変え、回り道をしたりして試しているうちにうまくいって、振り返ってみると・・・なんだそうだったのか、と。
ところで、誰も研究してないのかな?
意外と誰もやってなかったりして。
そんなの嘘っぱちだろ、誰が研究費を出す、ってなもんで。
誰もやっていなかったというわけでブルーオーシャン。
私も昔は、UFOを研究しているおじさんにお金を払っていましたが、結局何も残さず旅立ってしまいました。自分だけUF0に乗って、火星の恋人のもとへ飛んでいきました。
そのおじさんの、その装置をはかりに載せて通電すると、少しずつ重量が減っていく、と。
ただそこだけ見るとスゴイけれど、よく考えてみたまえ。ボウルを流用したそのケース。
IC回路が軽くなるんだったら、あんなボウルを取り付ける必要もなく、基板だけはかりに載せれば良かったわけで・・・ボウルをつけるのがポイントだった。
回路にはトランジスタだったりICを使ったりしていたけど、74LS04より7404のほうが軽くなりやすいって・・・要は発熱量。74LSは省電力。
そう、熱気球の実験をしているようなもの。温められた空気は軽くなる。ただそれだけ。
別の実験で、鉄の針金でコイルを巻いて通電したら、もっと軽くなったという。まさにヒーター。ICより発熱は大きい。銅より鉄は抵抗が大きい。
そこで、
「はかりじゃなくて、天秤のように左右に同じ物(同じ重量の物)を吊るして、電源は電池にして左右つりあわせておいて、片方だけスイッチONしたらどうです、軽くなれば傾くから、見た目でわかりやすくないですか」って投稿したことがある。
その投稿がおじさんのゴキゲンを損ねたのか、単なる手違いなのかは今となってはわからないが、次の会報だけ送ってこなかった。
けっこう、核心を突いたのでは、と自分で思っている。
装置をさかさまにしたらどうか、ICの基板を裏返しに取り付けても同じ結果か、というのは当時思いついたかどうかわからないけど、言ったら言ったで面倒なことになったかもしれないな。
インチキだとわかっててやっていたのかもしれない。今となってはわからない。
いや、インチキだなんて言うのは次元が低い。
私はこう考えている。宗教だったんだ。あのおじさんは教祖だった。
UFOを作るという夢を共有する仲間が教祖の下に集まって、一緒に夢をみよう、楽しもうというのが目的だったのだろう。
わかってるんだからさ、そんな露呈するような実験をしたら雰囲気ぶちこわしだろ。夢がさめちゃうだろ。
夢を見る、その意味では楽しかったと思う。それでいい。
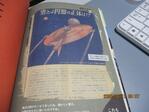
このイラストでは何か噴射してるけど、それは違うだろうと。
証言に基づいた想像図なので、必ずしも実物を示したものではないが、噴射するあたりは既成概念にとらわれているようだ。
やっぱり反重力か何かで、何も噴射せず、フワリと浮いてビュンと飛んでいかなきゃ空飛ぶ円盤じゃない。
どんな原理で飛んでいるのか、それは地球の人類にはまだわかってない。(エリア51あたりでは既に常識だろうけどな)
でも私は思います。それは案外、簡単なことかもしれません。
あー、なーんだ、そんなことだったのか。
わかってしまえば簡単だけれど、今はわかる前の段階、わからないからわからないという、何がわからないのかわからない、そんな感じ。
案外そんなものです。
新しいことに取り組む時、本を読んでも全然わからないし、試してみてもサッパリだし、なかなか思ったような結果がでないし、それでも執着して手を変え品を変え、回り道をしたりして試しているうちにうまくいって、振り返ってみると・・・なんだそうだったのか、と。
ところで、誰も研究してないのかな?
意外と誰もやってなかったりして。
そんなの嘘っぱちだろ、誰が研究費を出す、ってなもんで。
誰もやっていなかったというわけでブルーオーシャン。
私も昔は、UFOを研究しているおじさんにお金を払っていましたが、結局何も残さず旅立ってしまいました。自分だけUF0に乗って、火星の恋人のもとへ飛んでいきました。
そのおじさんの、その装置をはかりに載せて通電すると、少しずつ重量が減っていく、と。
ただそこだけ見るとスゴイけれど、よく考えてみたまえ。ボウルを流用したそのケース。
IC回路が軽くなるんだったら、あんなボウルを取り付ける必要もなく、基板だけはかりに載せれば良かったわけで・・・ボウルをつけるのがポイントだった。
回路にはトランジスタだったりICを使ったりしていたけど、74LS04より7404のほうが軽くなりやすいって・・・要は発熱量。74LSは省電力。
そう、熱気球の実験をしているようなもの。温められた空気は軽くなる。ただそれだけ。
別の実験で、鉄の針金でコイルを巻いて通電したら、もっと軽くなったという。まさにヒーター。ICより発熱は大きい。銅より鉄は抵抗が大きい。
そこで、
「はかりじゃなくて、天秤のように左右に同じ物(同じ重量の物)を吊るして、電源は電池にして左右つりあわせておいて、片方だけスイッチONしたらどうです、軽くなれば傾くから、見た目でわかりやすくないですか」って投稿したことがある。
その投稿がおじさんのゴキゲンを損ねたのか、単なる手違いなのかは今となってはわからないが、次の会報だけ送ってこなかった。
けっこう、核心を突いたのでは、と自分で思っている。
装置をさかさまにしたらどうか、ICの基板を裏返しに取り付けても同じ結果か、というのは当時思いついたかどうかわからないけど、言ったら言ったで面倒なことになったかもしれないな。
インチキだとわかっててやっていたのかもしれない。今となってはわからない。
いや、インチキだなんて言うのは次元が低い。
私はこう考えている。宗教だったんだ。あのおじさんは教祖だった。
UFOを作るという夢を共有する仲間が教祖の下に集まって、一緒に夢をみよう、楽しもうというのが目的だったのだろう。
わかってるんだからさ、そんな露呈するような実験をしたら雰囲気ぶちこわしだろ。夢がさめちゃうだろ。
夢を見る、その意味では楽しかったと思う。それでいい。
トラックバックURL
トラックバック一覧
コメント一覧
kanitama - 2025年08月13日 11:35
昭和な子供たちは「ぽんぽん船」や「しょうのう船」などに興じたものです。船はスクリューや風で動くものだと思い込んでいたちびっこには衝撃的です。きっと宇宙人がどこかでこっそり教えてくれることで新しい推進原理を見つけることができるでしょう。でしょう..でしょう..でしょう.....。
コメント投稿
 2025.08.13 05:56
|
2025.08.13 05:56
| 



