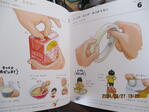ジョイスティックポートのアナログ入力
2024.03.28
中学生の頃、確か雑誌の記事を参考にしたと思うけど、ジョイスティックポートからアナログ信号を取り込む手段がある事を知った。
MSXのテクハンなどに載っているけど、ワンショットのIC(MC14538等)を利用する。可変抵抗(ボリューム)を回すと、その状態を数値として取り込むことができる。
これでCDS(光導電素子/明るさで抵抗値が変わる)をつないで遊んだり、サーミスタ(温度センサ)もつないでみたと思うけど、
一定時間ごとにデータを取り込み、グラフを描いて遊んだりした。
そうだ、こいつで毎日の気温測定をしたらどうか。夏休みの自由研究にちょうど良い。楽ができる。(という思いつき、単純な頭だった)
ところが、この用途のためだけにMSXを占有しておくわけにもいかない。いまのPCと違いシングルタスクだから、他のことができない。早々にあきらめたと思う。
まあ、でも、夕方に光センサをセットしておき、徐々に暗くなっていく様子が画面に描かれるのを見たりして面白かった。
この当時に使っていたのは、やはりHB-101。
MSXのテクハンなどに載っているけど、ワンショットのIC(MC14538等)を利用する。可変抵抗(ボリューム)を回すと、その状態を数値として取り込むことができる。
これでCDS(光導電素子/明るさで抵抗値が変わる)をつないで遊んだり、サーミスタ(温度センサ)もつないでみたと思うけど、
一定時間ごとにデータを取り込み、グラフを描いて遊んだりした。
そうだ、こいつで毎日の気温測定をしたらどうか。夏休みの自由研究にちょうど良い。楽ができる。(という思いつき、単純な頭だった)
ところが、この用途のためだけにMSXを占有しておくわけにもいかない。いまのPCと違いシングルタスクだから、他のことができない。早々にあきらめたと思う。
まあ、でも、夕方に光センサをセットしておき、徐々に暗くなっていく様子が画面に描かれるのを見たりして面白かった。
この当時に使っていたのは、やはりHB-101。
HB-101とリレー
2024.03.28
自分がパソコンを使って何かを制御するという試みは、HB-101のカセットI/Fのリレーを利用したのが最初だったと思う。
MOTOR ONとMOTOR OFFを実行するとON/OFFする。
ONとOFFの時間を調整し、キーボードで打った文字のモールス信号を送るプログラムを作ったりした。
当時、内部のリレーにどこまで電流を流してよいかわからない。下手して壊すといけないので、外付の回路を自作した。
今度はプリンタポートを利用した。これなら8本は使える。STBも入れれば9本。
アンフェノール14Pのコネクタがないと始まらない。これは確か共立電子から通販で買ったと思う。
BUSYを常時GNDに落としておけば、LPRINTでドンドン出力できる。そのうちにOUT命令を使うようになったと思うけど、よく覚えていない。
最初はLEDをつないでチカチカさせて遊んだが、次にリレーをつないでみた。リレーというものは意外と高いので、3個か4個並べて精一杯だったと思う。それでもカチカチ鳴って、合奏みたいになって面白かった。
リレーの電源はMSXから取らないで別に準備した電池を利用したと思う。
MOTOR ONとMOTOR OFFを実行するとON/OFFする。
ONとOFFの時間を調整し、キーボードで打った文字のモールス信号を送るプログラムを作ったりした。
当時、内部のリレーにどこまで電流を流してよいかわからない。下手して壊すといけないので、外付の回路を自作した。
今度はプリンタポートを利用した。これなら8本は使える。STBも入れれば9本。
アンフェノール14Pのコネクタがないと始まらない。これは確か共立電子から通販で買ったと思う。
BUSYを常時GNDに落としておけば、LPRINTでドンドン出力できる。そのうちにOUT命令を使うようになったと思うけど、よく覚えていない。
最初はLEDをつないでチカチカさせて遊んだが、次にリレーをつないでみた。リレーというものは意外と高いので、3個か4個並べて精一杯だったと思う。それでもカチカチ鳴って、合奏みたいになって面白かった。
リレーの電源はMSXから取らないで別に準備した電池を利用したと思う。
自転車は宅配便で輸送できるか
2024.03.28
30年以上前、下宿屋の仲間が実家から自転車を送ってもらおうとしていた。
自転車があれば出かけるにも色々便利だよなあ、とか言いながら・・・
ところが、色々あって難しいようで、なかなか送ってこない。細かい事は忘れたが、宅配便業者が難色を示しているようだった。
それでも後日なんとか送られてきて、よかったねー、という話。
但し、料金がいくらかかったのかは不明。
いまはどうなっているだろう?
例:ヤマト運輸
送ること自体は可能だが、問題は料金。サイズや重量で通常の宅急便の適用外となれば、追加料金もかかるだろうし・・・要相談というところでしょうか。
梱包も課題でしょう。
金額を考えると、現地で安いのを買ってしまったほうが良い場合も。(ちなみに当時は金銭的余裕がなかったので買わないで送ってもらったのだ)
さて、送られてきてよかったねー、の後日談。
喜んで乗り回していたが、・・・
盗まれた。
確か最初はマウンテンバイク。盗まれた後、次に乗っていたのはママチャリだったが、これはもらったのか再び送ってもらったのかは忘れた。
どっちも、盗まれた。ガッカリ。
自転車があれば出かけるにも色々便利だよなあ、とか言いながら・・・
ところが、色々あって難しいようで、なかなか送ってこない。細かい事は忘れたが、宅配便業者が難色を示しているようだった。
それでも後日なんとか送られてきて、よかったねー、という話。
但し、料金がいくらかかったのかは不明。
いまはどうなっているだろう?
例:ヤマト運輸
送ること自体は可能だが、問題は料金。サイズや重量で通常の宅急便の適用外となれば、追加料金もかかるだろうし・・・要相談というところでしょうか。
梱包も課題でしょう。
金額を考えると、現地で安いのを買ってしまったほうが良い場合も。(ちなみに当時は金銭的余裕がなかったので買わないで送ってもらったのだ)
さて、送られてきてよかったねー、の後日談。
喜んで乗り回していたが、・・・
盗まれた。
確か最初はマウンテンバイク。盗まれた後、次に乗っていたのはママチャリだったが、これはもらったのか再び送ってもらったのかは忘れた。
どっちも、盗まれた。ガッカリ。
大ピンチずかんの実物を見る
2024.03.27
PC-286BOOKにSCSI
2024.03.27
これは相当古い。90年代前半の話。
その頃、SPC-SCSIというのが有って、MB89352を(本来SCSIが内蔵されていない機種に)組み込んで動かすのが流行っていました。
なんと、ワープロ専用機に組み込んだ人もいました。(当時トラ技の記事あり)
このためのSCSIドライバがフリーソフトで公開されていたので、本当に有り難かった。
ほかにもSCSI接続の試みは有って、EasyHardというのだが、ケーブル1本だけでSCSIのHDDをつなぐ。もはや専用ICすら不要。
ダイナブックのパラレルポートを利用したもので、電気的にはSCSIの規格を満たさないところもあるが一応動くというもの。
残念ながらPC98系では片方向しかデータが行かないので原理的にできませんでした。AT互換機はデータが双方向だったのでこんな事もできたんですね。
当時の私に依頼があったのは、PC-286BOOKというEPSONのPC98互換機にSCSIを組み込めないか、という話。パソコン通信仲間の学校の先生から。
オプションのモデムを組み込む部分があり、そこが引き出しのようになっているので、ここに何とか(基板とコネクタが)おさまらないか、と。
当時はサンハヤトの感光基板、その片面パターンでMB89352と終端抵抗や周辺ICを載せた基板を手作りしたものでした。
実際に作ってテストした時の写真が昔のネガの中に残っていました。


(お気づきかもしれないが、ネガを裏返しにしてしまった!)
確か、配布されていたドライバでは(PC286BOOK上では)I/Oアドレスが競合するので、自分でSYMDEBを使い、空いているI/Oアドレスにパッチを当てて書き換えたのでした。
これを含めて、2~3点ほど試行錯誤があったような記憶です。
思い出してみると、ソースをアセンブルしようにも86用のアセンブラがなかったか、有ったと思うけれど。手っ取り早いのはパッチだなと思ったんだろう。SYS(ドライバ)をデバッガに読み込み、逆アセンブルしながらI/Oアクセスの命令を探して、書き換えて、保存した、というのが手順。
今さらこんな事を書いても仕方ないけど、SCSIのHDDから起動はできません。(起動の為のROMはない)
まずフロッピーから起動して、SPC-SCSI用のドライバを組み込んでから初めてSCSIが使えるようになります。
それでも当時は不便とは思いませんでした。HDDやMOが使えるようになっただけで、まるで今までとは天と地のような差を感じました。
確か依頼主は小学校の先生だったかな。これを見たその先生の知り合いの先生も、自分も欲しいと言い出してもう1台作っておさめたような記憶です。
確か最初の1台だけは手配線で作ったはず。何度も手配線で作るのは大変だから、それで感光基板で何枚も作れるようにしたわけだ。
その頃、SPC-SCSIというのが有って、MB89352を(本来SCSIが内蔵されていない機種に)組み込んで動かすのが流行っていました。
なんと、ワープロ専用機に組み込んだ人もいました。(当時トラ技の記事あり)
このためのSCSIドライバがフリーソフトで公開されていたので、本当に有り難かった。
ほかにもSCSI接続の試みは有って、EasyHardというのだが、ケーブル1本だけでSCSIのHDDをつなぐ。もはや専用ICすら不要。
ダイナブックのパラレルポートを利用したもので、電気的にはSCSIの規格を満たさないところもあるが一応動くというもの。
残念ながらPC98系では片方向しかデータが行かないので原理的にできませんでした。AT互換機はデータが双方向だったのでこんな事もできたんですね。
当時の私に依頼があったのは、PC-286BOOKというEPSONのPC98互換機にSCSIを組み込めないか、という話。パソコン通信仲間の学校の先生から。
オプションのモデムを組み込む部分があり、そこが引き出しのようになっているので、ここに何とか(基板とコネクタが)おさまらないか、と。
当時はサンハヤトの感光基板、その片面パターンでMB89352と終端抵抗や周辺ICを載せた基板を手作りしたものでした。
実際に作ってテストした時の写真が昔のネガの中に残っていました。


(お気づきかもしれないが、ネガを裏返しにしてしまった!)
確か、配布されていたドライバでは(PC286BOOK上では)I/Oアドレスが競合するので、自分でSYMDEBを使い、空いているI/Oアドレスにパッチを当てて書き換えたのでした。
これを含めて、2~3点ほど試行錯誤があったような記憶です。
思い出してみると、ソースをアセンブルしようにも86用のアセンブラがなかったか、有ったと思うけれど。手っ取り早いのはパッチだなと思ったんだろう。SYS(ドライバ)をデバッガに読み込み、逆アセンブルしながらI/Oアクセスの命令を探して、書き換えて、保存した、というのが手順。
今さらこんな事を書いても仕方ないけど、SCSIのHDDから起動はできません。(起動の為のROMはない)
まずフロッピーから起動して、SPC-SCSI用のドライバを組み込んでから初めてSCSIが使えるようになります。
それでも当時は不便とは思いませんでした。HDDやMOが使えるようになっただけで、まるで今までとは天と地のような差を感じました。
確か依頼主は小学校の先生だったかな。これを見たその先生の知り合いの先生も、自分も欲しいと言い出してもう1台作っておさめたような記憶です。
確か最初の1台だけは手配線で作ったはず。何度も手配線で作るのは大変だから、それで感光基板で何枚も作れるようにしたわけだ。
 2024.03.28 19:50
|
2024.03.28 19:50
|