ダンボールは捨てろ
2024.09.04
溜まりがちなダンボール
だけど、整理しないから溜まっていく。(その都度捨てろ)
とりあえずタダで手に入る物入れとしても、溜まっていく。(物を保管するなら管理が必須)
ダンボールは「G」の住処にもなる。
荷造りに必要な最低限のダンボールだけ残しておき、必ずたたんだ状態で保管しておく。
ダンボールは買うまでもなく、スーパーからもらってくれば良いので、多くを手元に置く必要はない。(でも、厚手の丈夫なダンボールや細長いダンボールはなかなか手に入らないから、捨てずに残しておく)
物を保管する入れ物は、たとえば折りたたみ式のコンテナにする。あるいは透明のボックスにする。(中身が見えるようにするのと、必ず中身をラベルに書いておく)
RSコンポーネンツの箱なんか「たこやき」のトレイに似た感じで、通称「たこやき」と呼んで活用していたが、
さすがにたくさん集まってくると見苦しくなり、どれに何が入っていて、何に使う分なのか、必要なのか不要なのかもわからない状態となったので、スパッとやめてしまいました。
だけど、整理しないから溜まっていく。(その都度捨てろ)
とりあえずタダで手に入る物入れとしても、溜まっていく。(物を保管するなら管理が必須)
ダンボールは「G」の住処にもなる。
荷造りに必要な最低限のダンボールだけ残しておき、必ずたたんだ状態で保管しておく。
ダンボールは買うまでもなく、スーパーからもらってくれば良いので、多くを手元に置く必要はない。(でも、厚手の丈夫なダンボールや細長いダンボールはなかなか手に入らないから、捨てずに残しておく)
物を保管する入れ物は、たとえば折りたたみ式のコンテナにする。あるいは透明のボックスにする。(中身が見えるようにするのと、必ず中身をラベルに書いておく)
RSコンポーネンツの箱なんか「たこやき」のトレイに似た感じで、通称「たこやき」と呼んで活用していたが、
さすがにたくさん集まってくると見苦しくなり、どれに何が入っていて、何に使う分なのか、必要なのか不要なのかもわからない状態となったので、スパッとやめてしまいました。
昔の無線リモコン試作
2024.09.04

これも昔作ったもので、確か1998年頃だったかと。
当時315MHzのリモコン用送信・受信モジュールが市販されていて(今も中国製など有るだろうけど)、
その評価のために作ったのが、これらの基板。ひとつは送信、もうひとつは受信。
現在のように便利なTWE-LITEとかWi-Fi、Bluetoothは当時なかった。
電波リモコンやデータ送受信には苦心があった。
単純にシリアル通信の信号を電波に乗せてもうまく通信できない。当時は未熟だったから、そのあたりもよくわかっていなかった。
電波の伝わり方も一定じゃないから、思ったように受信できなくて当たり前。当時は当たり前とは思っていなかった。なぜだろうと思いながら試行錯誤するばかり。
これをもとに設計した製品、微弱電波の試験をTELECで受けようとして連絡をとったのは覚えているけど、
本当に微弱電波の基準を満たすと、実用性の点では劣るという認識がある。
市販のワイヤレスチャイムやカメラなどいろいろあるけど、試買調査でかなりの物が微弱電波の基準をオーバーしているもんなあ。
だからって許されるわけじゃないけど、微弱の基準って厳しくないかと思う。だったら特定小電力にしろってなるんだろうけれど。
家の中どこでも届くようにしろ、というのもなかなか(微弱では)厳しいときがあり、木造もあれば鉄筋もあるし、二階建てだけでなく三階建てもあるでしょう。
中継機を設けたりというのも有りだけれど。
今度は周波数がダブったりして、空き周波数を探すのなら受信回路も必要じゃないかと。あるいは複数の周波数に同じ信号を分散して送って、下手な鉄砲数撃ちゃ当たる作戦とか。
Ni-MHの充電回路
2024.09.04
これは20年以上前の残骸
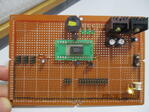
当時ポケットサイズの何かを作っていて(身障者用の器具)、できるだけ小型にする必要があった。
最初に作った試作は、寄せ集めでとりあえず動くものを作ったという感じで、見たら笑われるような物体だった。
タカチのプラケースにおさまらなくて、もうひとつ同じケースを輪切りにして、それでケースをつないで深さをかせいだ。つぎはぎ細工。
さらに小型化という事で、たばこの箱ぐらいにした。たばこの箱といっても色々あるが・・・普通に見かけるサイズ。
そこで電池はニッケル水素の単4を4本使う事にした。
当時リチウムイオンやリチウムポリマーは世の中に存在したかもしれないが、現在のように容易に入手できず採用できなかった。
秋葉原の某店でニッケル水素の単4を4本パックにしてもらい、それを組み込んだ。
もうひとつの課題は充電回路だった。
秋月の充電回路や放電回路のキットは作ったけど、その回路をそのまま組み込むスペースは無かった。
ほかの回路もスペースを取るので、充電回路に使えるスペースは限られていた。できるだけ簡単な回路にしたい。
それで改めてICを選定して、データシートを解読しながら設計を進めた次第。
英語はよくわからなかったが、必死になって英文を解読した。当時は実用的な翻訳サイトはなかった。あやしげな翻訳結果を見ながら、うーんと考えて、解釈をした。
充電はできるようになったけど、熱くなりすぎたりといった問題もあり、悩んでいた。
前置きが長くなったけど、その充電回路をもう一度よく検討しようとして作ったのが、冒頭の試作基板。結局、作りかけのままで20年以上放置・・・
あとでやろうというのがだめ。いつまでもやらない。取り組むなら今やらないと。
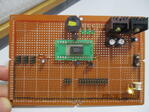
当時ポケットサイズの何かを作っていて(身障者用の器具)、できるだけ小型にする必要があった。
最初に作った試作は、寄せ集めでとりあえず動くものを作ったという感じで、見たら笑われるような物体だった。
タカチのプラケースにおさまらなくて、もうひとつ同じケースを輪切りにして、それでケースをつないで深さをかせいだ。つぎはぎ細工。
さらに小型化という事で、たばこの箱ぐらいにした。たばこの箱といっても色々あるが・・・普通に見かけるサイズ。
そこで電池はニッケル水素の単4を4本使う事にした。
当時リチウムイオンやリチウムポリマーは世の中に存在したかもしれないが、現在のように容易に入手できず採用できなかった。
秋葉原の某店でニッケル水素の単4を4本パックにしてもらい、それを組み込んだ。
もうひとつの課題は充電回路だった。
秋月の充電回路や放電回路のキットは作ったけど、その回路をそのまま組み込むスペースは無かった。
ほかの回路もスペースを取るので、充電回路に使えるスペースは限られていた。できるだけ簡単な回路にしたい。
それで改めてICを選定して、データシートを解読しながら設計を進めた次第。
英語はよくわからなかったが、必死になって英文を解読した。当時は実用的な翻訳サイトはなかった。あやしげな翻訳結果を見ながら、うーんと考えて、解釈をした。
充電はできるようになったけど、熱くなりすぎたりといった問題もあり、悩んでいた。
前置きが長くなったけど、その充電回路をもう一度よく検討しようとして作ったのが、冒頭の試作基板。結局、作りかけのままで20年以上放置・・・
あとでやろうというのがだめ。いつまでもやらない。取り組むなら今やらないと。
かぶとえびは微妙
2024.09.04
改めて「かぶとえび」を調べてみると、
その写真・・・
なんというか、あの「G」を連想してしまいました。
触覚と、あのボディと色と。
ゾゾッ・・・
その写真・・・
なんというか、あの「G」を連想してしまいました。
触覚と、あのボディと色と。
ゾゾッ・・・
アリの巣観察キット
2024.09.04
小学生の頃、学研の「ふろく」だった物を思い出したが・・・
早速試したけれど、結局アリが入ってくれなくて、それっきりになってしまった。
でも、
台所を見ると、砂糖にアリが群がっているんだよなあ。
砂糖があれば簡単に集まってくるじゃないか。
だけど、なんで私の「アリの巣」には入ってくれないんだろうと。
砂糖も入れてみたような気がするけど、結局、相手にされなかったのでした。
もし、うまくアリの巣ができたら、観察が終わった後・・・
「ヌハハハハ、アリの世界は終わりだ~」とか言いながら中身を地面にぶちまけ、ないけど。
ムスカみたいだ。アリがアリのようだ。そりゃそうだ。
あとひとつ、
かぶとえび飼育セットもうまくいかなくて、今でも心残りだ。
卵が含まれている田んぼの土が入っていて、それに水を入れたと思う。
半分ぐらい太陽の光が当たるように置く。
ちゃんと書いてある通りに準備したんだけれど。
なんか数ミリの小さいのがチョロッと動いているのは見た覚えがあるけど、あれはかぶとえびじゃなかったのだと思う。どう見てもパッケージや説明の写真に載っている姿と違う。
通学路に沿って田んぼが続いていたけど、その田んぼでもかぶとえびを見た記憶はない。
もともといなかったのか、農薬の影響でいなくなったのかは不明。
ざりがに、ってのも本には載っていたが、やはり見た覚えはない。
スルメにタコ糸をつけて、釣り上げるとかなんとか。やってみたくても、ざりがにがいなかったらどうしようもない。
いたのは、おたまじゃくしぐらいかな。
早速試したけれど、結局アリが入ってくれなくて、それっきりになってしまった。
でも、
台所を見ると、砂糖にアリが群がっているんだよなあ。
砂糖があれば簡単に集まってくるじゃないか。
だけど、なんで私の「アリの巣」には入ってくれないんだろうと。
砂糖も入れてみたような気がするけど、結局、相手にされなかったのでした。
もし、うまくアリの巣ができたら、観察が終わった後・・・
「ヌハハハハ、アリの世界は終わりだ~」とか言いながら中身を地面にぶちまけ、ないけど。
ムスカみたいだ。アリがアリのようだ。そりゃそうだ。
あとひとつ、
かぶとえび飼育セットもうまくいかなくて、今でも心残りだ。
卵が含まれている田んぼの土が入っていて、それに水を入れたと思う。
半分ぐらい太陽の光が当たるように置く。
ちゃんと書いてある通りに準備したんだけれど。
なんか数ミリの小さいのがチョロッと動いているのは見た覚えがあるけど、あれはかぶとえびじゃなかったのだと思う。どう見てもパッケージや説明の写真に載っている姿と違う。
通学路に沿って田んぼが続いていたけど、その田んぼでもかぶとえびを見た記憶はない。
もともといなかったのか、農薬の影響でいなくなったのかは不明。
ざりがに、ってのも本には載っていたが、やはり見た覚えはない。
スルメにタコ糸をつけて、釣り上げるとかなんとか。やってみたくても、ざりがにがいなかったらどうしようもない。
いたのは、おたまじゃくしぐらいかな。
 2024.09.04 13:26
|
2024.09.04 13:26
| 



