ISH形式
2024.11.26
これも、今ではほとんど誰もわからない話かもしれない。
自分の草の根ネットにはファイル専用のボードがあったけど、他のホスト用のプログラムでは掲示板のみという時代もあったようです。
そこへなんとかしてファイルをアップできないかというわけで、ISH形式というものがありました。
普通のファイルだと、テキストではないファイルという意味ですが、コントロールコードや表示できない文字も当然含まれます。そのままでは掲示板に載せられないし、表示が乱れるばかりです。欠落もあるでしょう。
そこでファイルを一旦、可読文字に置き換えてしまい、掲示板への掲載もできるようにした、というふうに私は理解しています。
ダウンロードしたい人は、それをログにとっておき、ISHのプログラムを使うと元のファイルに戻せるというものでした。
アクセスの最初から最後までの通信内容をログといってファイルに記録しておき、それをISHのプログラムにかけると、ISH形式の部分からファイルを抽出してくれるのでした。
ISH形式は、いますぐには具体例を探し出せませんが、
879SFS9AR892J9U98FSDU98GSD8762GJHFJKHASDKFHAS
SA8786Y238HYRIOWEYAU87YFSAHIOFHSDAUF8Y721OIUY
FJDSAIY20ROIHAHFSD8OYH2OI8RWIQOFDSHAA2GANVXKJ
・・・のような文字の羅列でした。
いまで言うところのBASE64エンコードにあたるでしょうか。
その当時でもバイナリからテキストへの変換としては、インテルHEXやモトローラS形式というものがありました。これは主にプログラミングの世界で、ROMの書き込みに使っていたのであまり一般的ではなかったかもしれない。
自分の草の根ネットにはファイル専用のボードがあったけど、他のホスト用のプログラムでは掲示板のみという時代もあったようです。
そこへなんとかしてファイルをアップできないかというわけで、ISH形式というものがありました。
普通のファイルだと、テキストではないファイルという意味ですが、コントロールコードや表示できない文字も当然含まれます。そのままでは掲示板に載せられないし、表示が乱れるばかりです。欠落もあるでしょう。
そこでファイルを一旦、可読文字に置き換えてしまい、掲示板への掲載もできるようにした、というふうに私は理解しています。
ダウンロードしたい人は、それをログにとっておき、ISHのプログラムを使うと元のファイルに戻せるというものでした。
アクセスの最初から最後までの通信内容をログといってファイルに記録しておき、それをISHのプログラムにかけると、ISH形式の部分からファイルを抽出してくれるのでした。
ISH形式は、いますぐには具体例を探し出せませんが、
879SFS9AR892J9U98FSDU98GSD8762GJHFJKHASDKFHAS
SA8786Y238HYRIOWEYAU87YFSAHIOFHSDAUF8Y721OIUY
FJDSAIY20ROIHAHFSD8OYH2OI8RWIQOFDSHAA2GANVXKJ
・・・のような文字の羅列でした。
いまで言うところのBASE64エンコードにあたるでしょうか。
その当時でもバイナリからテキストへの変換としては、インテルHEXやモトローラS形式というものがありました。これは主にプログラミングの世界で、ROMの書き込みに使っていたのであまり一般的ではなかったかもしれない。
1行ボード(掲示板)
2024.11.26
当時、草の根ネットに設置していた1行ボードと呼ばれる掲示板
今で言うX(旧Twitter)のような感じで、1行程度の短い文章を投稿することができました。
意外と利用が多かったような印象があります。
通常の掲示板のほうは各分野ごとに設置しており、会員の中でも特に登録された者しか入れない空間もありました。
ちなみにメールボックスも有り、閉局に際してはとうとう相手に受信されないまま残ったメールもあったと思います。(閉局前に、各自受信するように呼びかけはしていた)
今では考えられないけれど、すべて文字ベースのやりとりでした。
絵や写真はファイルボードといって、ファイルを保管するスペースがあり、そこへアップロードしていました。リアルタイムに見る事はできず、ダウンロードしてから見ていました。
ファイルボードの利用では主にフリーソフトの交換を行っていました。
初期の頃、市販ソフトをアップロードした不届き者がいて、厳重に注意しました。本人に直接言ってもケロリとしていて、暖簾に腕押しでした。ちょっと感覚が違うようです。とにかくやめろって言ったんですがね。一度削除したら、またアップロードするし。
本人に聞くと「ローカルの者しか見ないから良いだろ」とか、そうじゃないだろって、なかなか本人には話が通じませんでした。
最初はそいつにチャットで呼びかけた。やりとりをしていたら意外と家が近い事がわかったので遊びに来ないかと誘ってみたら、
来た本人は全く無口というかコミュニケーション能力に問題ありの引きこもりで、場がもたない。こっちが話さないと何も言わない。おとなしすぎる。
とんでもないやつを呼んでしまったと後悔したが、基本的には悪い奴ではなさそうで、それだけは救いだったが・・・
ネット弁慶というか、いまでもネット上で強気や攻撃的なコメントをしてくるやつはたいていこのタイプだろうなと思っている。リアルでは他人とまともに会話もできない。
フリーソフトや自作のイラスト等、正当なものであっても、
大きいサイズのファイルのダウンロードで長時間回線を占有するのは良くないこととされており、譲り合って使いましょうと呼びかけていました。いまでは意味がわからないことですね。
物理的に電話回線が数本しかないのと、夜間は特に利用が集中するので、話し中になりがちでした。
つながらないと、接続したくなくなるから回線を増やして会員を受け入れろって、それで最終的には3回線(アナログ1回線とISDNで2回線分)にしました。
ちなみに大きいサイズのファイルといっても1メガとかそんなものでした。当時は通信速度が今と比べて遅いから、ずいぶん時間がかかったのです。
メガバイトのファイルなんて少なかった。たいていは数キロから数十キロバイトのファイルばかり。
そりゃあ、確かに画像は荒かったかもしれないが、色数も少なかったし・・・でも今から振り返ってみるとそれはそれで味わいがあった。
JPG画像1枚表示するだけでも遅くて、JPGはなるべく見たくないなと思ったりしていました。これはPCの処理速度の問題。
今で言うX(旧Twitter)のような感じで、1行程度の短い文章を投稿することができました。
意外と利用が多かったような印象があります。
通常の掲示板のほうは各分野ごとに設置しており、会員の中でも特に登録された者しか入れない空間もありました。
ちなみにメールボックスも有り、閉局に際してはとうとう相手に受信されないまま残ったメールもあったと思います。(閉局前に、各自受信するように呼びかけはしていた)
今では考えられないけれど、すべて文字ベースのやりとりでした。
絵や写真はファイルボードといって、ファイルを保管するスペースがあり、そこへアップロードしていました。リアルタイムに見る事はできず、ダウンロードしてから見ていました。
ファイルボードの利用では主にフリーソフトの交換を行っていました。
初期の頃、市販ソフトをアップロードした不届き者がいて、厳重に注意しました。本人に直接言ってもケロリとしていて、暖簾に腕押しでした。ちょっと感覚が違うようです。とにかくやめろって言ったんですがね。一度削除したら、またアップロードするし。
本人に聞くと「ローカルの者しか見ないから良いだろ」とか、そうじゃないだろって、なかなか本人には話が通じませんでした。
最初はそいつにチャットで呼びかけた。やりとりをしていたら意外と家が近い事がわかったので遊びに来ないかと誘ってみたら、
来た本人は全く無口というかコミュニケーション能力に問題ありの引きこもりで、場がもたない。こっちが話さないと何も言わない。おとなしすぎる。
とんでもないやつを呼んでしまったと後悔したが、基本的には悪い奴ではなさそうで、それだけは救いだったが・・・
ネット弁慶というか、いまでもネット上で強気や攻撃的なコメントをしてくるやつはたいていこのタイプだろうなと思っている。リアルでは他人とまともに会話もできない。
フリーソフトや自作のイラスト等、正当なものであっても、
大きいサイズのファイルのダウンロードで長時間回線を占有するのは良くないこととされており、譲り合って使いましょうと呼びかけていました。いまでは意味がわからないことですね。
物理的に電話回線が数本しかないのと、夜間は特に利用が集中するので、話し中になりがちでした。
つながらないと、接続したくなくなるから回線を増やして会員を受け入れろって、それで最終的には3回線(アナログ1回線とISDNで2回線分)にしました。
ちなみに大きいサイズのファイルといっても1メガとかそんなものでした。当時は通信速度が今と比べて遅いから、ずいぶん時間がかかったのです。
メガバイトのファイルなんて少なかった。たいていは数キロから数十キロバイトのファイルばかり。
そりゃあ、確かに画像は荒かったかもしれないが、色数も少なかったし・・・でも今から振り返ってみるとそれはそれで味わいがあった。
JPG画像1枚表示するだけでも遅くて、JPGはなるべく見たくないなと思ったりしていました。これはPCの処理速度の問題。
内線の交換機
2024.11.26
NTTの回線に接続することなく、電話機、モデムやFAX同士の通信テストができるようにする装置を擬似交換機といいます。
もしNTTの回線でテストしようと思ったら、2回線引く事になり、さらに通話料などもかかります。もし開発中の機器だったら勝手に接続できません。(技術基準適合認定)
それにダイヤルミス等で他人に迷惑をかけてしまう事もあってはなりません。
私は仕事上、疑似交換機を持っています。
そのほか、昔あった「三角電伝」(TRI-JACK)、そしてISDNのターミナルアダプタ(IT55DSU等)でも内線通話を利用する事ができました。
自分の草の根ネットでも、SYSOP(私)が接続する時は内線を利用して接続していました。基本的にはクロスケーブルを使うようになっていましたが、TAのアナログポートにモデムをつないでいたので外線と内線をそのまま使えて便利でした。電話番号を変えるだけ。
クロスケーブルだったらつなぎ替えか、あるいは当時流行った切替スイッチで切り替える必要があり、当初はそのようにしていたと思います。
究極的にはモデム同士を直結しても通信可能です。2台のモデムを接続する場合、片方はATDで発信、もう片方はATAで応答します。
あるいはFAXモデムを使い、FAXをスキャナまたはプリンタ代わりにしたい場合(これも'90年代に流行った)、FAXとFAXモデムを直結します。
回線の電流を監視している機種はそのままでは駄目で、下記の方法で実施します。
その線に6V~9V程度の電池に抵抗を通してつないでやると通信できました。当然、ベルを鳴らしたりはできません。発信・着信は手動で操作します。
FAX機のほうは受話器を上げてスタートボタンを押します。
もしNTTの回線でテストしようと思ったら、2回線引く事になり、さらに通話料などもかかります。もし開発中の機器だったら勝手に接続できません。(技術基準適合認定)
それにダイヤルミス等で他人に迷惑をかけてしまう事もあってはなりません。
私は仕事上、疑似交換機を持っています。
そのほか、昔あった「三角電伝」(TRI-JACK)、そしてISDNのターミナルアダプタ(IT55DSU等)でも内線通話を利用する事ができました。
自分の草の根ネットでも、SYSOP(私)が接続する時は内線を利用して接続していました。基本的にはクロスケーブルを使うようになっていましたが、TAのアナログポートにモデムをつないでいたので外線と内線をそのまま使えて便利でした。電話番号を変えるだけ。
クロスケーブルだったらつなぎ替えか、あるいは当時流行った切替スイッチで切り替える必要があり、当初はそのようにしていたと思います。
究極的にはモデム同士を直結しても通信可能です。2台のモデムを接続する場合、片方はATDで発信、もう片方はATAで応答します。
あるいはFAXモデムを使い、FAXをスキャナまたはプリンタ代わりにしたい場合(これも'90年代に流行った)、FAXとFAXモデムを直結します。
回線の電流を監視している機種はそのままでは駄目で、下記の方法で実施します。
その線に6V~9V程度の電池に抵抗を通してつないでやると通信できました。当然、ベルを鳴らしたりはできません。発信・着信は手動で操作します。
FAX機のほうは受話器を上げてスタートボタンを押します。
草の根ネットに内線で接続できた
2024.11.25
26年ぶりの設定で初心者同然でしたが、試行錯誤してようやく着信できるようになりました。
先日はクロスケーブル接続まではできていたのだけど(これも苦労したが)、まだモデム着信までできていなかったのでした。
'92年か'93年に初めて着信テストをしたときも、最初の設定がうまくできていなかったのかもしれない。
同僚に彼の自宅からかけてもらって、何度も試したが、なかなか着信がうまくいかない。おかしいなあ。あの時は初めてだったし、何か基本的な事を間違っていたんだろうと思うが・・・ひとつはAA(自動着信)の設定で、自動着信「しない」にしなければならない。
えっ、ホスト局だから自動着信でしょ、って思うじゃないですか。当時の自分もそう信じこんでいた。ところが間違いだった。
モデムの自動着信設定は、モデム自身が自動的に着信する機能。
草の根ネットのホストでは、手動着信にしなければならない。手動って言ってもホストプログラムがやる。着信時のRINGまたはRS-232CのRI信号が来たら、ATAというコマンドをモデムに送って着信させる。これがその手順だ。
モデムの初期値で自動着信ONになっている機種が有り、これは自宅の回線につないでおくと(PCとは関係なしに)電話がかかってきた時に勝手にモデムが電話をとってしまう。結果として相手にはピーーーと聞こえるだけで、人間が出ないとなってしまうトラブルもあった。
だから初期値としてはOFFにするべき。
さて、
KTBBSの起動時、モデムには初期化コマンドが送られるはずだけどLEDを見ていても動きがみられないから、なぜだろうと考えて、設定を見直したりしました。
何度も見直してようやくわかった!
WindowsのPCに付けたUSBモデムから発信・・・ホスト局(PC98)のモデムが応答し、あの懐かしいピーガーヒョロロー音(涙)
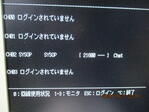
ほぼ直結のような接続なのに21600か。ノイズかな。
最初は文字化けして、なぜだろうと思ったら・・・シフトJISにしなければならなかった。Windows側の通信ソフトの設定がUTF-8だと文字化けします。PC98の世界はシフトJISだった。
次の画面は、あの伝説の「SYSOP呼び出し」の様子

チャットからSを押すとホスト局のPC98がピッピッピッと鳴り出すのです。
当時の会員さんたちは、深夜でも遠慮なくこの機能を使って起こしにかかってきました。
こちらが応答しないと、「起きてるくせに」とか独り言を書き込んだりして、まあこちらも起きていて見てたりとか・・・(笑)

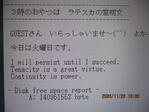
先日はクロスケーブル接続まではできていたのだけど(これも苦労したが)、まだモデム着信までできていなかったのでした。
'92年か'93年に初めて着信テストをしたときも、最初の設定がうまくできていなかったのかもしれない。
同僚に彼の自宅からかけてもらって、何度も試したが、なかなか着信がうまくいかない。おかしいなあ。あの時は初めてだったし、何か基本的な事を間違っていたんだろうと思うが・・・ひとつはAA(自動着信)の設定で、自動着信「しない」にしなければならない。
えっ、ホスト局だから自動着信でしょ、って思うじゃないですか。当時の自分もそう信じこんでいた。ところが間違いだった。
モデムの自動着信設定は、モデム自身が自動的に着信する機能。
草の根ネットのホストでは、手動着信にしなければならない。手動って言ってもホストプログラムがやる。着信時のRINGまたはRS-232CのRI信号が来たら、ATAというコマンドをモデムに送って着信させる。これがその手順だ。
モデムの初期値で自動着信ONになっている機種が有り、これは自宅の回線につないでおくと(PCとは関係なしに)電話がかかってきた時に勝手にモデムが電話をとってしまう。結果として相手にはピーーーと聞こえるだけで、人間が出ないとなってしまうトラブルもあった。
だから初期値としてはOFFにするべき。
さて、
KTBBSの起動時、モデムには初期化コマンドが送られるはずだけどLEDを見ていても動きがみられないから、なぜだろうと考えて、設定を見直したりしました。
何度も見直してようやくわかった!
WindowsのPCに付けたUSBモデムから発信・・・ホスト局(PC98)のモデムが応答し、あの懐かしいピーガーヒョロロー音(涙)
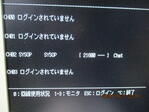
ほぼ直結のような接続なのに21600か。ノイズかな。
最初は文字化けして、なぜだろうと思ったら・・・シフトJISにしなければならなかった。Windows側の通信ソフトの設定がUTF-8だと文字化けします。PC98の世界はシフトJISだった。
次の画面は、あの伝説の「SYSOP呼び出し」の様子

チャットからSを押すとホスト局のPC98がピッピッピッと鳴り出すのです。
当時の会員さんたちは、深夜でも遠慮なくこの機能を使って起こしにかかってきました。
こちらが応答しないと、「起きてるくせに」とか独り言を書き込んだりして、まあこちらも起きていて見てたりとか・・・(笑)

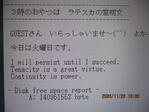
USRoboticsのモデム
2024.11.25
もはや誰もわからない世界になってきたが・・・
パソコン通信の全盛期(前世紀?)に、一部マニアが大好きだったUSRoboticsのモデム。
うるさい人が多かったような印象。
これで某ネットに接続して、一番いいのはコレだとか何だとか色々。
モデムマニアの私だが、じつは一度も手を出したことがなかったという不思議な関係。今頃になって、いまさら現物を入手。
外装フィルムが破られてない未開封品だったが、開けてみると・・・アッ!

ACアダプタが割れてる。中身が見えてる。
よく見ると割れてない方もヒビが入っている。
おそらく、かなり強い衝撃が加わったものと思われます。ACアダプタは特に重いので、ダメージを受けやすかったか。
モデム本体は割れてない。大丈夫。

昔から思うけど妙なデザインだ。なんかラジオみたい。側面にボリューム調整が有るし、スピーカーが組み込まれているのでラジオっぽい。
そして、本体はビニールに包まれておらずそのまま箱の中に入っていた。日本製だったらビニールに包まれているのが普通だ。
モデム内部をのぞいてみました。

このメーカーはDSPによる独自の信号処理で、他のモデムメーカーとは一線を画していました。他社はほとんどロックウェルのチップセットを使っていました。
まあ、これも今では昔話。ソフトモデムになってしまったから、もう関係ないといえば関係ない。
電源アダプタどうしよう。かけらを割れたところにテープで貼っておこう。(だめ)
もともと日本向け仕様ではなく、米国のAC120V用なので電圧ギリギリかもしれない。無負荷では実測でAC9Vだった。無負荷だからなあ。もうちょっと余裕がほしい。
これはトランス式のACアダプタ。今では多くがスイッチング式で軽く小さく大容量になったが、昔はトランス式ばかりだった。ラジカセや留守番電話など。
いまの時代、トランス式のACアダプタはほとんど見かけない。有っても高価だ。
なぜトランス式かというと、ひとつはノイズ対策のため。スイッチング式は原理上どうしてもノイズが乗ってくる。アナログ回路に対しては、一般的にはトランス式の電源が良い。
もっとも、スイッチング式だって近頃は良いものが出てきている。でも基本はそうだ。
特に注意が必要なのは、AC出力ということ。これはトランスの出力そのまま出ているはず。
昔ながらのACアダプタは、トランスの二次側にブリッジダイオードと大型の電解コンデンサが入っている。それで完全ではないがDCとなっている。(脈流)
トランス式でも近頃では珍しいのに、その中でもAC出力というのは更に希少といえる。
まあでも、トランスを買ってきて自分でアルミケースに組み込んで「自作」(つく)れば良い。多少不格好でも、自作は愛着が湧く。
パソコン通信の全盛期(前世紀?)に、一部マニアが大好きだったUSRoboticsのモデム。
うるさい人が多かったような印象。
これで某ネットに接続して、一番いいのはコレだとか何だとか色々。
モデムマニアの私だが、じつは一度も手を出したことがなかったという不思議な関係。今頃になって、いまさら現物を入手。
外装フィルムが破られてない未開封品だったが、開けてみると・・・アッ!

ACアダプタが割れてる。中身が見えてる。
よく見ると割れてない方もヒビが入っている。
おそらく、かなり強い衝撃が加わったものと思われます。ACアダプタは特に重いので、ダメージを受けやすかったか。
モデム本体は割れてない。大丈夫。

昔から思うけど妙なデザインだ。なんかラジオみたい。側面にボリューム調整が有るし、スピーカーが組み込まれているのでラジオっぽい。
そして、本体はビニールに包まれておらずそのまま箱の中に入っていた。日本製だったらビニールに包まれているのが普通だ。
モデム内部をのぞいてみました。

このメーカーはDSPによる独自の信号処理で、他のモデムメーカーとは一線を画していました。他社はほとんどロックウェルのチップセットを使っていました。
まあ、これも今では昔話。ソフトモデムになってしまったから、もう関係ないといえば関係ない。
電源アダプタどうしよう。かけらを割れたところにテープで貼っておこう。(だめ)
もともと日本向け仕様ではなく、米国のAC120V用なので電圧ギリギリかもしれない。無負荷では実測でAC9Vだった。無負荷だからなあ。もうちょっと余裕がほしい。
これはトランス式のACアダプタ。今では多くがスイッチング式で軽く小さく大容量になったが、昔はトランス式ばかりだった。ラジカセや留守番電話など。
いまの時代、トランス式のACアダプタはほとんど見かけない。有っても高価だ。
なぜトランス式かというと、ひとつはノイズ対策のため。スイッチング式は原理上どうしてもノイズが乗ってくる。アナログ回路に対しては、一般的にはトランス式の電源が良い。
もっとも、スイッチング式だって近頃は良いものが出てきている。でも基本はそうだ。
特に注意が必要なのは、AC出力ということ。これはトランスの出力そのまま出ているはず。
昔ながらのACアダプタは、トランスの二次側にブリッジダイオードと大型の電解コンデンサが入っている。それで完全ではないがDCとなっている。(脈流)
トランス式でも近頃では珍しいのに、その中でもAC出力というのは更に希少といえる。
まあでも、トランスを買ってきて自分でアルミケースに組み込んで「自作」(つく)れば良い。多少不格好でも、自作は愛着が湧く。
 2024.11.26 07:39
|
2024.11.26 07:39
| 



